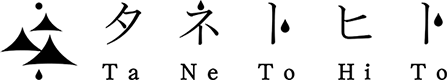タネトヒトとは
生きとし生ける人、
それぞれの場所で、
それぞれの日常があります
その日常と並行して、
悠久の自然が息づく、
もう一つの時間が流れています
タネトヒトは、
たおやかで逞しい里山の環境を通して、
その2つの時間を結ぶ、
種まきをしています


この土地で田をつくりお米をお届けすること、
里山に身を置いていただく体験の時間をつくること、
それが私たちの種です
皆さんの暮らしの土壌に、
種が芽吹き、自然と人、人と人がつながりが
結ばれることを願っています

タネトヒトという名前の由来は、代表である小障子が不登校と引きこもりを経験したことに始まり、教育や学びとはいかなるものかということへの疑問を問う中で、ある書籍の中の一節に共感したことに由来します。
その一節は、簡潔に述べると、親が子に与える最良のこととは塾に行かせることや、いわゆる偏差値の高い学校に進学させること、望むものを買い与えることなどではなく、人との出会いや、それまで経験したことがない様々な経験の種を数多く撒いてあげること、そのことに尽きるのではないかというものでした。
たくさん撒かれた種が発芽するかもしれないし発芽しないかもしれない、けれどもいつか発芽したときに、その芽がその子の心の支えや生きる糧になるかもしれない。それは、敬愛する写真家の星野道夫の一説にも通じるものがあります。

子どもの頃に見た風景が、ずっと心の中に残ることがある。いつか大人になり、さまざまな人生の岐路に立った時、人の言葉でなく、いつか見た風景に励まされたり勇気を与えられたりすることがきっとあるような気がする
星野道夫 著『旅をする木』文春文庫 1999年 P118
私自身は、農や里山の環境の中で、人と人、人と自然がつながる種まきをしたいと思い、タネトヒトという名で、これまでの農業とは違う在り方を模索し、形作っていければと思っています。
ここを訪れた人の中に、小さな種が宿り、いつかその目が発芽し大きく育ってくれることを夢見て、今日もまた田と向き合っていきます。
タネトヒト・代表 小障子正喜
会社情報
| 会社名 | 株式会社タネトヒト |
|---|---|
| 設立 | 2025年11月10日 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市小谷上山田町881 |
| 資本金 | 500万円 |
| 代表者 | 小障子正喜、小障子菜々子 |
| 事業内容 |
|
プロフィール

小障子正喜(コショウジ マサヨシ)
1978年大阪育ち
中学2年生の時に不登校となり、20歳まで引きこもりの生活を送る。その後、地元の夜間高校に入学し、大学・大学院へと進学。タネトヒトの前身である農事組合法人大戸洞舎の研修事業(どっぽ村プロジェクト)に参加し、研修途中で社員となりその後代表となる。株式会社タネトヒトに組織を変更し、今後は既存の農業生産と里山と農業をベースとした体験事業の展開を図る。

小障子菜々子(コショウジ ナナコ)
1978年滋賀育ち
18歳まで上山田で暮らし、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)情報デザインを経て、東京にてエンターテイメントのデザイン会社に勤務。30歳を目前に、地域の役に立ちたいと思うようになりUターン。地域産業のパッケージを中心としたデザインに携わる。手を動かして里山にある資源と親しむことがライフワーク。日本の豊かな里山が次世代に継がれることを願っている。